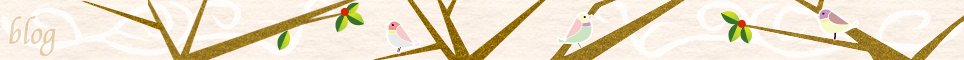
TOP >ブログ
2021年5月20日
山陽堂書店メールマガジン【2021年5月20日配信】
山陽堂書店メールマガジン【2021年5月20日配信】
こんにちは。
今日は今年これまでに読んだなかで特にお気に入りのこちらを。
『どうしようもないのに、好き』内田洋子・集英社文庫

著者 内田洋子さんはイタリアでのニュースを日本に配信するジャーナリ
2011年には『ジーノの家 イタリア10景』でエッセイスト・
本書の副題は「イタリア 15の恋愛物語」。
交友関係も広く、知人の子どもたちの〈保護者代理人〉
長いイタリア生活の中で目にしてきた恋愛にまつわる15篇の人間
描写される登場人物の体躯、身に纏う衣服、仕草、
訪れた部屋や招かれた食卓での様子は各人の所作とともに描かれ、
その時の状況を緻密に描写し再現できるのはジャーナリスト故でし
収められたいくつかの話を少しだけ。
「腹ふくるる思い」
記者である友人の女性にはふたりの娘。
年子の姉妹は性格も身体つきも顔も似たところがない。
きれいなほうと、そうでないほう。
一番近くにいる人から、そう区別されていた。
10年ぶりに再会した"そうでないほう"の妹 オルガは、結婚をし、ふたりの子どもにも恵まれ、
しかし、
「母や姉の言う通り、私は何をしても駄目なのよ」
そう語る彼女は、少し泣いていた。
(小さな時分から周囲にどうみなされてきたか。
「目は口ほどに」
書物に造詣が深く国内外で高く評価されているという眼科医。
知人から紹介されたその医師の私邸に招かれた際に、
目の前にいる自分を見てくれてはいないという悲しみに、
彼は誰の目も求めていないのか、
(妻の振る舞いにまた虚しさが募ります。)
「海と姉妹」
美しい海があり、
島南部の漁村出身で、一代で財を成し、
訪ねた自宅では妻リリに対し金切り声を上げ昼食の準備を促し、
庭での昼食が済むと、
それを見送ってから、リリは内田さんに声をかける。
「こちらでコーヒーをいかがです?」
台所のテーブルでコーヒーを飲みながら語られるダヴィデとリリの
その途中、リリの妹がやってきて席に着く。
続けて語られた、かつてあった島への工場誘致計画の話。
ある不幸を招くことになったその話を語るリリと、沈んだ顔の妹。
ダヴィデとリリ、そしてリリの妹。
「お姉さん、私は本当に何も覚えていないのよ」
(ふたりの姉妹の美しい姿が目に浮かび、
「赤い糸」
心震わせることがある度に手首にブレスレットを付け足す女子高生
幼馴染のマウロとのやり取りを目にした内田さんは、
その年の夏の終わり、
彼女から聞くマウロと過ごした休暇中の話と、
(ふたりが並んで話をしている様子が目に浮かび、
どの話にもいつの間にか引き込まれてしまいます。
意外な展開を迎える話も多く、最後の1ページに幾度も「なんと...
どうやってこんな話を聞き出し、書き上げられるののだろう?
それは内田さんが相手(他者)と絶妙な距離感を築けることと、
義理堅く情に厚いこと、
ただそれだけではなく、どんな状況に置いても"なにか"
今回、15篇の主な登場人物に共通して感じたのは、
普段は包み隠されていたり陽の光に紛れてしまっているような悲し
本人さえも気づいていないかもしれない影こそが、
ちなみに、
「私は小説家ではありませんから、
なるべく写真のキャプションを書くような気持ちで、
実際に見聞きした事実が内田さんの言葉で丁寧(緻密)
だから物語・
以前紹介した「モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語」もそうでしたが、
読後の余韻も僕にとってはまた格別で、つまり僕は、
昨年の4月頃より毎週木曜日に配信していた山陽堂書店メールマガ
次号よりGALLERY SANYODOでの展示情報や新商品のお知らせを中心に不定期で
山陽堂書店
萬納 嶺
2021年5月13日
山陽堂書店メールマガジン【2021年5月13日配信】
山陽堂書店メールマガジン【2021年5月13日配信】
こんにちは。
本日5月13日発売の本を紹介します。
「晴れた日にかなしみの一つ」上原隆・双葉文庫

「自分を道端にころがっている小石のようだと感じたとき、
この問題意識を手にして、様々な人に話を聞いてみることにした。
そう語る上原さんは、
そして、出会った人たちの話を短い文章でまとめるこの形を「
今回刊行された本書には20の話が書かれています。
「声にならない悲鳴」
38歳のときに研究者になることを諦めて民間企業に就職した男性
自分なりに考えながら行っていることがうまくいかなかったり周囲
男性はその思いを帰りの電車の中で1冊のノートに書き綴っており
ノートのページというページから江藤の叫び声がきこえてくる。
(中略)
多くの職場で、怒られてじっと黙って仕事をしている人がいる。
能力がないといわれて我慢している人がいる。
おそらく、同じ職場の優秀な人たちは、
ノートに綴られた文字は読んでいてなかなかつらいのですが、
上原さんの言葉で言うところの「自分を支える杖」
別れ際、上原さんがかけた言葉に男性は一瞬びっくりした顔をし、
「婚活しても結婚できない」
上原さんの結論に「確かにそうかもしれないな...」と妙に納得。
「別れ話は公園で」
20代の男女の別れ話が彼女側の視点(心の声)
恋愛に器用とはいえなそうな彼女が心に思う言葉は、
"こういう苦さ"を思い出してしまいました。
「八年目のファックス」
新婚旅行から帰ってきた直後に27歳の若さで亡くなってしまった
彼女の実家には命日になると毎年、
ふたりは30近く歳が離れていたものの互いにタメ口で話し、「
上原さんは「どうして毎年」とその元上司に尋ねます。
八年目もまたファックスが届きます。
「ログハウス」
自殺してしまった父親が八ヶ岳の麓に土地を買って建てたログハウ
上原さんはそこに同行し、
命を絶つ直前に電話があったにも関わらず男性はその声を聞くこと
好きだからこそ父親の行為を少なからず肯定したいと考える男性の
上原さんはあとがきのなかでこう書いています。
「困難なときに自分を支えるもの、それがどんなものであっても、
これがノンフィクション・
10代の頃からずっと表現することを仕事にしたいと思っていた上
自分の表現というものがつかめないまま「
そしてそんな自分を振り返った時に「痛いな」と思うともに、
それが冒頭の言葉に繋がります。
「自分を道端にころがっている小石のようだと感じたとき、
この問題意識を手にして、様々な人に話を聞いてみることにした。
ほとんど誰しもが経験する"挫折"が出発点であり、
だからこそ、読んでいて登場人物と自分自身を(部分的にでも)
自分をころがっている小石だと感じたり、
ちょっとしたことや、何も起きていないときにさえ(
僕もこれまで何度も思うことがありましたし、
「なんか、虚しいな」と。
そんなときには上原隆さんの本を。
「まぁ、それでも歩いていくか」と思わせてくれます。
※
・山陽堂書店メールマガジン【2021年6月22日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年5月20日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年5月13日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年4月15日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年4月8日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年4月1日配信】
・〈展示作品紹介〉春の安西水丸展⑦ SIS企画展「スノードームのある風景」
・山陽堂書店メールマガジン【2021年3月25日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年3月18日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年3月11日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年5月20日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年5月13日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年4月15日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年4月8日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年4月1日配信】
・〈展示作品紹介〉春の安西水丸展⑦ SIS企画展「スノードームのある風景」
・山陽堂書店メールマガジン【2021年3月25日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年3月18日配信】
・山陽堂書店メールマガジン【2021年3月11日配信】
・2021年6月 (1)
・2021年5月 (2)
・2021年4月 (4)
・2021年3月 (3)
・2021年2月 (6)
・2021年1月 (4)
・2020年12月 (5)
・2020年11月 (4)
・2020年10月 (5)
・2020年9月 (5)
・2020年8月 (5)
・2020年7月 (5)
・2020年6月 (4)
・2020年5月 (4)
・2020年4月 (3)
・2018年10月 (2)
・2018年9月 (1)
・2018年6月 (1)
・2018年1月 (1)
・2017年3月 (1)
・2017年2月 (1)
・2015年5月 (1)
・2014年9月 (1)
・2014年7月 (1)
・2014年5月 (1)
・2014年2月 (1)
・2013年8月 (1)
・2013年6月 (2)
・2013年5月 (1)
・2013年4月 (1)
・2013年3月 (2)
・2013年1月 (1)
・2012年12月 (1)
・2012年11月 (1)
・2012年10月 (2)
・2012年9月 (4)
・2012年8月 (4)
・2012年7月 (2)
・2012年6月 (1)
・2012年5月 (6)
・2012年4月 (3)
・2012年3月 (1)
・2012年2月 (1)
・2012年1月 (2)
・2011年12月 (1)
・2011年11月 (3)
・2011年10月 (3)
・2011年9月 (2)
・2011年8月 (2)
・2011年7月 (2)
・2011年5月 (1)
・2011年4月 (3)
・2011年3月 (9)
・2011年2月 (12)
・2021年5月 (2)
・2021年4月 (4)
・2021年3月 (3)
・2021年2月 (6)
・2021年1月 (4)
・2020年12月 (5)
・2020年11月 (4)
・2020年10月 (5)
・2020年9月 (5)
・2020年8月 (5)
・2020年7月 (5)
・2020年6月 (4)
・2020年5月 (4)
・2020年4月 (3)
・2018年10月 (2)
・2018年9月 (1)
・2018年6月 (1)
・2018年1月 (1)
・2017年3月 (1)
・2017年2月 (1)
・2015年5月 (1)
・2014年9月 (1)
・2014年7月 (1)
・2014年5月 (1)
・2014年2月 (1)
・2013年8月 (1)
・2013年6月 (2)
・2013年5月 (1)
・2013年4月 (1)
・2013年3月 (2)
・2013年1月 (1)
・2012年12月 (1)
・2012年11月 (1)
・2012年10月 (2)
・2012年9月 (4)
・2012年8月 (4)
・2012年7月 (2)
・2012年6月 (1)
・2012年5月 (6)
・2012年4月 (3)
・2012年3月 (1)
・2012年2月 (1)
・2012年1月 (2)
・2011年12月 (1)
・2011年11月 (3)
・2011年10月 (3)
・2011年9月 (2)
・2011年8月 (2)
・2011年7月 (2)
・2011年5月 (1)
・2011年4月 (3)
・2011年3月 (9)
・2011年2月 (12)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
